ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
生命と非生命のあいだ(小林憲正)
『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか (ブルーバックス B 2258)』2024/4/18
小林 憲正 (著)
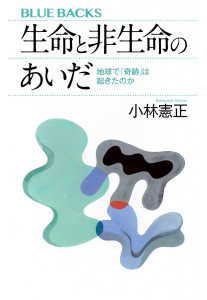
(感想)
地球に生命が誕生したことは「奇跡」なのか?「必然」なのか?……「生命の起源」についての仮説として圧倒的な支持を集める「RNAワールド」が説明できないこの問いに、アストロバイオロジー第一人者の小林さんが「生命の起源」研究の全貌と何が論点なのかを分かりやすく整理して、「究極の謎」に迫っている本です。
生命がRNAから始まったとする「RNAワールド仮説」では、条件を満たすRNAをつくるには、ヌクレオチドを少なくとも40個正しい順番でつなぐ必要があり、それは非常に難しいそうです。次のようにも書いてありました。
「最初の生命は生物進化によっては誕生できないので、自然発生したと考えるしかありません。しかし、自然発生はパストゥールの実験によって、否定されています。地球上では生命の自然発生ができないのならば、生命は地球外から持ち込まれたのではないか?」
……ということで、宇宙からの生命の種が地球にたどり着いたという「パンスペルミア説」まであるのですが、宇宙から来たとしても、その「生命の種」はいったいどうやって出来たのかが分からないそうです……その通りですね(笑)。
さて生命の誕生に必要なものは……
「(前略)「地球型」生命の誕生には、リン脂質、タンパク質、そして核酸が必要であることがわかります。とりわけタンパク質と核酸は、両者がともにそろわなければ生体内でつくることができないものでもあり、地球生命の根源をなす分子と考えられます。」
……ということで、現在は「RNAワールド仮説」がかなりの支持を集めているようです。その理由は……
「(前略)核酸にはDNAとRNAがありますが、この2つに関してはRNAが先ということは間違いないとされています。RNAとDNAではDNAのほうが安定性が高い。つまり変化しにくいからです。最初になんらかの機能を持った核酸ができるまでは、試行錯誤が必要だったでしょうから、変化しやすいRNAのほうが適しています。しかし、いったん機能を有するものができたあとでは、下手に変化されては困るので、より安定性の高いDNAの形で情報をしまい込むのが得策です。」
……しかも酵素の働きもしているRNA(リボザイム)も見つかっています。
RNAは代謝と自己複製のどちらの機能も持っていますが、生命なき世界で最初のRNA分子をつくるのは、あまりにも難しいそうです。例えばタンパク質の場合は、「アミノ酸をつくる」「つなげる」の2段階だけで良いのですが、RNAの場合は、「核酸塩基をつくる」「糖(リボース)をつくる」「核酸塩基とリボースをつなげてヌクレオシドをつくる」「ヌクレオシドにリン酸をつなげてヌクレオチドをつくる」「ヌクレオチドをつなげる」の5段階が必要だからです。
それでも最新の研究によると、ヌクレオチドは生命誕生以前の環境条件でつくれることが分かってきて(ただし何段階もの反応を温度やpHを変えながら進める必要がありますが……)、陸上の温泉地帯(しかもカリウムが高いところ)が有力な「生命誕生の場」になっているようでした(陸上の方が、有機物を濃縮したり、水を抜きながらつなぎあわせたりしやすいから)。
また深海底の熱水噴出孔も有力候補ですが、それは、熱水噴出孔から吹き出す海水がメタン・アンモニア・水素を高濃度に含むほか、鉄や亜鉛・銅・マンガンなどさまざまな金属イオン(生物の必須元素)を通常より高濃度に含むという好条件があるからのようです。またすべての生物がもっているリボソームRNAの塩基配列を用いた分子系統樹では、バクテリア、アーキアのどちらの枝でも、根元に近い生物は80℃以上のお湯の中で繁殖する「超好熱菌」が多いことが分かっているのだとか。
そして最近の研究では、宇宙線の入ってくるところでは、どこでもアミノ酸ができる可能性があることが分かってきたそうです。
「(前略)宇宙の分子雲や小惑星でも、アミノ酸などの有機物生成の鍵を握るのは、宇宙線などの放射線だったのです。」
……放射線や宇宙線は高エネルギーなので、どんな分子でもその結合を切ったり、電子を剥ぎ取ったりできます。こうして、いったんばらばらにされたものは、安定になろうとして再結合するので、さまざまな大きい分子(がらくた分子)が出来るようです。
これが小林さんの「がらくたワールド」という考え方につながって、この「がらくた分子」が、ゆるやかに生命誕生の元になっていったのではないかというのです。
「(前略)多様である、つまり膨大なライブラリーが存在すれば、それぞれの分子はほんのわずかでも、また、低い活性であったとしても、さまざまな触媒機能を持つ分子が含まれているはずです。その中には、自己触媒により自分自身をつくる機能を持つものがあっても不思議ではありません。するとその分子は、初めはゆっくり、やがて急速に量を増やすことになります。」
「(前略)RNAワールドに至る道筋には、ほかにもさまざまな経路があると考えられます。多種多様な分子のライブラリーから、さまざまな経路に沿って、自己複製あるいはその前段階としての自己触媒の能力を持つ分子が少しでも発生すれば、それらが、そうでない分子よりも最初はわずかに頭角を現し、やがて急速に増えていくでしょう。」
……さまざまな「がらくた分子」が、さまざまな機能をもつ生物につながっていったのかもしれません。
「地球外生命も膜、代謝、自己複製にあたるなんらかのしくみを持っている可能性は高いでしょう。しかし、生命が誕生したときにこれらの機能がすべて同時に発生したとは考えにくいので、いろいろな特徴を部分的に持ったものが多様に存在したのではないかと私は考えています。」
*
『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』……「RNAワールド」はなぜ、どのように起こったのかを科学的に深く考察している本で興味津々でした。生命進化についても幅広く復習することが出来ました。面白くて勉強にもなる本なので、みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『生命と非生命のあいだ』