ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
描画参考資料
教養としての日本の文様(小松大秀)
『教養としての日本の文様』2024/12/15
小松 大秀 (著)
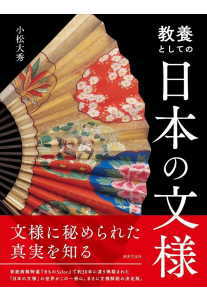
(感想)
美しい着物や帯、漆器などのフルカラー写真とともに、その模様にまつわる説明を読むことができる本で、主な内容は次の通りです。
第1章 祝いの心を形で見せる「吉祥文様」
コラム「知っておきたい文様と模様(正倉院文様、有職文様、王朝模様)」
第2章 四季を愛で、生命を慈しむ「季節の文様」
第3章 物語や詩歌の情景を愛でる「文芸の文様」
第4章 線と面によるジャパニーズデザイン「幾何文様」
*
松竹梅や鶴亀文様から、桜や紅葉など季節を表す文様、そしてグラフィカルな市松文様まで、さまざまな文様の意味やルーツを教えてもらえました。
ただ……模様をきっちりカテゴリー分けして解説している「文様図鑑」という感じではなく、エッセイ集のような感じで、図鑑というよりは読み物という印象でしたが、それもそのはず、これは「きもの総合誌『家庭画報特選 きものSalon』で30年に渡り掲載してきた「日本の文様」を保存版として一冊の書籍」にしたものだそうです。
この本は、その模様が使われている着物や帯、漆器などの小物の写真が美しくて、とても見応えがありました。解説の方も説明文というよりは、エッセイ風の文体なので、気楽な気分で楽しみながら読み進められます。
例えば「第1章 祝いの心を形で見せる「吉祥文様」」では……
「桐竹」の項目で、「古代中国では、天子を象徴する鳥――鳳凰――は、桐の樹に棲み、竹の実を食う、とされてきたこと」や、「高貴な鳥をあからさまに描かず、拠となる植物だけを描いてその存在を暗示する」手法などについて知ることができました。
また「松と鶴の組合せ=蓬莱山のイメージ」だそうですが、これは……
「蓬莱山といえば、亀の骨に峻険な岩山を乗せた形が普通ですが、その周りに松喰鶴が群れをなして舞っている」からだそうです。
そして「四君子(蘭、竹、梅、菊)」では……
「(前略)四君子、すなわち蘭、竹、梅、菊は、草木のなかでも清らかで高潔な、まさに君子のようなイメージがあって、隠居楽道には欠かせないアイテムでした。」
さらに「歳寒三友(松竹梅)」では……
「(前略)歳寒三友とは、厳寒にあっても常緑を保つ松や天に伸びる竹、寒さのなか花を咲かせる梅のこと。苦境にあっても節操を保つ清冽な姿が理想的な文人の生き方として、尊ばれていました。」
また「コラム「知っておきたい文様と模様(正倉院文様、有職文様、王朝模様)」)では、「有職文様」について……
「(前略)ここで紹介する有職文様は、有職の知識に基づく公家文化の中で用いられ、装束や調度・器物などに表現された文様をさします。有職文様でもっとも重要なことは、身分が決められた公家社会の中で、特定の有職文様がそれを用いる本人の身分や立場・役割を、他の人が目で見てわかるように定められ、使用が厳格に制限されていたことです。」
……なお、その頂点に位置するのは、天皇陛下がお召しになる「桐竹鳳凰麒麟文」なのだとか。
『教養としての日本の文様』……着物や漆芸、絵画など、どれも国内屈指といえる一級の美術品の写真とともに、文様に関するエッセイ風の解説を読むことができて、楽しみながら教養を深められそうな本でした。日本の文様に興味がある方は、ぜひ読んで(眺めて)みてください☆
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『教養としての日本の文様』