ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
古生物はこんなふうに生きていた(ロマックス)
『古生物はこんなふうに生きていた:化石からよみがえる50の場面』2025/3/3
ディーン・R・ロマックス (著), ボブ・ニコルズ (イラスト), 藤原多伽夫 (翻訳), & 1 その他
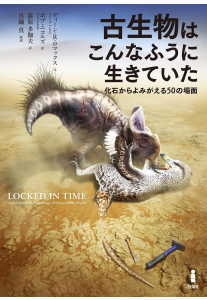
(感想)
古生物学者のロマックスさんが、当時の行動をそのまま残した驚くべき化石50個をピックアップして、古生物のリアルな姿を解説してくれる本で、世界屈指の古生物復元アーティストのニコルズさんによる、科学的に正確なイラストも迫力満点です。
なかでも印象的だったのが「ジュラ紀のカブトガニが最後に残した歩行跡」。ロマックスさんが一八歳だった頃、初めてのアメリカ旅行で訪れた博物館で目を奪われ、彼が化石を生物学的に研究する道を進むことになる「きっかけ」をつくった化石です。
「(前略)歩行跡の特定の場所、とりわけ終点に近い場所で脚の跡が深くなっている。これはおそらく、カブトガニが泳いで海底を離れようと軟らかい泥を蹴った場所を示しているのだろう。しかし、泳ぎ去るだけのエネルギーは残っていなかった。歩行の行動の変化は、カブトガニが無酸素の有毒な水域で苦しみ始め、瀕死の体をゆっくり引きずって泥の上を進んでいったことを示している。そして最後には窒息して命が尽きた。
起点から終点までの歩行跡全体とともに、跡をつけた動物自身も保存されたこの化石は、太古の動物が命を終えるまでの最後のひとこまを伝える唯一無二の標本だ。」
……ドラマチックな化石ですね……(写真とイラストで見ることができます)。
またユーモラスに見える「一列になった状態で保存された三葉虫」の化石は、長距離を集団で移動中だったと推定されています。
「五億年以上前、動物は最初の脳と感覚器官を進化させた。こうした性質を生かし、これらの初期の節足動物は複雑な形の集団行動を発達させ、移動する集団を形成して、急速に変化する世界で生存と繁殖の可能性を高めていったのだ。」
……なるほど。確かに、「集団行動」は全員にある程度の知能がないと出来ませんよね……。
そして驚いたのが「脱皮中の化石」。
「カンブリア紀の節足動物が脱皮している姿が化石に残されていることから、脱皮は節足動物の進化の初期段階で起きていたことが裏づけられた。実際に化石が見つかるまで、これは推定でしかなかった。脱皮の一部始終を記録したジュラ紀のメコキルスとその生痕化石は、太古の節足動物の生涯で欠かせない行動を見事に垣間見せてくれる。」
……化石は、その行動が、進化的にいつ頃起こったのかを教えてくれるんですね……
また迫力があったのが、一万二000年前に対決したままの状態を見せてくれる二頭のマンモスの化石。
「二頭のマンモスは互いに牙を絡ませて、じかに接触した状態で保存されている。一頭は右の牙が完全に残っているが、左の牙は折れている。もう一頭は左の牙が完全に残っているが、右の牙は折れている。折れた牙の根元は縁がとがっておらず丸みを帯びている。これはつまり、牙は戦いのはるか前に折れていたということだ。このように珍しく両者の牙が損傷していたため、二頭は牙を直接ぶつけずに近づくことが出来た。牙が絡まってしまったのはこのためだ。恐ろしいことに、一本の牙の先端が相手の眼窩に刺さっている!」
……怖いですね!
この他、戦っている二頭の恐竜(プロトケラトプス、ヴェロキラプトル)の化石もあって、どうやら戦いの最中に砂丘が崩れて、二頭とも押し流されて埋もれたようです。
しまいには、なんと化石になった「おなら」まで見つかっています。それは「琥珀」に入ったシロアリ、ゴキブリ、アリ、ハナバチ、甲虫、ハエの放出したおならで、これが見つかったことにより、太古の昆虫も腸内の微生物の活動によってガスを放出したことが確認されたそうです……うーん、なんか……凄い化石があるものですね……。
『古生物はこんなふうに生きていた:化石からよみがえる50の場面』……化石を通して過去の現象をタイムマシンのように垣間見せてくれる本で、とても面白くて勉強にもなる本でした。古生物が好きな方は、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『古生物はこんなふうに生きていた』