ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
知られざるサメの世界(佐藤圭一)
『知られざるサメの世界 海の覇者、その生態と進化 (ブルーバックス B 2289)』2025/3/21
佐藤 圭一 (著), 冨田 武照 (著)
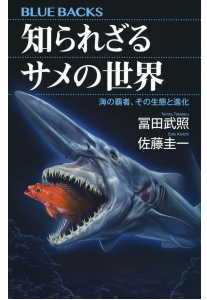
(感想)
サメの機能形態・生態・分類・繁殖について専門的・網羅的に解説してくれる本です。
鋭い歯のある巨大な口、流線型の体と長い背びれの美しいシルエット……サメは、最も長寿の脊椎動物であり、もっとも速く泳ぐ魚類の一つでもあるそうです。大きくて美しい「サメの歯」は、海のそばのお土産物でもたまに売っていることがありますが、実はサメの歯は使い捨てのようです。次のように書いてありました。
「(前略)サメにとって歯が破損することはそれほど大きい問題ではない。彼らの歯は生涯抜け替わり、歯が壊れてもすぐに新品に置きかわるからだ。シロワニというサメの観察によれば、おおよそ2日で1本の歯が抜けるらしい。使用中の歯が上下の顎で約50本とすれば、4カ月もすればすべての歯が新品に入れ替わる計算になる。」
……えー、そうだったんだ。
また本書の表紙のイラストのような、ものすごい顎をもつサメも実在しているようで……
「(前略)多くのサメは顎を射出させることができる。ホホジロザメが口を大きく開けた写真を見ると、顎全体が前にせり出して歯が?き出しになっているようすを見ることができる。このような動きは、顎が頭蓋骨(正確には脳頭蓋)から分離していることによって可能になっている。平常時、顎は頭蓋骨の後方にピッタリ収納されているのだが、摂餌の瞬間には、顎はもとあった場所から外れ、前方に射出される。」
……ひゃー、そんな食べ方をするサメがいるんですね。
そして次のようなサメの体の構造にも興味津々でした。
まず、サメが水中で沈まない謎については……
「一般に動物の体を構成している筋肉や骨格は水より重く、水中生物はそれ以外の場所で体を軽くする工夫をしている。たとえば、多くの硬骨魚類は気体の入った袋(浮袋)を体内に持つことで、浮きも沈みもしない中性浮力に近づけている。一方、サメは油を巨大な肝臓に溜め込むことによって、比重を小さくする努力をしている。」
*
そしてサメの血液循環や心拍については……
・「陸上生物の場合、鰓の代わりの役割を担っているのが肺である。心臓を出た血液は、まず肺に向かう。この血液は肺の細い血管を通過し、そこで酸素を受け取る。サメと決定的に異なるのはこの後だ。肺を通った血液はそのまま全身に送られるのではなく、一度心臓に戻される。そこで再度加圧されてから全身に送り出されるのだ。前半の心臓→肺→心臓の血液の流れを肺循環、広範の心臓→全身→心臓の血液の流れを体循環と呼ぶ。
ではサメは、鰓による圧力損失の問題をどのように解決しているのだろうか。この謎は十分に解かれていないように思われる。遊泳による規則的な体の動きが、血液を循環させるポンプの役割を果たしているという説もある。」
・「我々の調査によれば、ジンベエザメの心拍数は季節によって大きく変動するようで、夏の間は18回くらいまで上昇するが、冬は7回程度まで減少する。(中略)体温が高い夏の時期は、体が欲する酸素量が増えるから、心拍数を上げて、より多くの血液を体に循環させなければならない。一方、冬は酸素の必要量が減るから、心臓が送り出さなければならない血液量も少なくなるというわけだ。」
*
そして寒さ対策は……
・「(前略)化学反応の速度は基本的に温度に依存する。大雑把にいえば、一般に化学反応速度は10度下がるごとに、約半分に下がってしまう。これは、温度の低い場所で生活している生物にとっては大きな制約になっている可能性がある。実際、変温動物であるサメのエネルギー消費量は、海水温が10度下がるごとにおおよそ半分になることが知られている。」
・「(前略)彼ら(注:サメ)の多くは深海を餌場としており、時に表層より20度以上も冷たい水域に潜らなければならないこともある。水深ロガーを外洋性のサメに装着すると、深海に一気に潜ってしばらく過ごしたのちに、また一目散に表層に戻って来るということを一日に何度も繰り返す、「ヨーヨー遊泳」と呼ばれる行動が見られる。これは、深海でしばらく時間を過ごすと体温が下がってしまうので、定期的に表層に戻って体を温めている行動であると解釈されている。」
*
そして最も驚かされたのは、サメには卵生と胎生が混在する系統が多くみられるということ。次のように書いてありました。
「特に、多様性の高いメジロザメ目では、トラザメ類ではおもに卵生が占めているが、ドチザメ類では両者が混在し、メジロザメ類では胎生種のみとなる。このように、サメの系統樹上では頻繁に卵生→胎生、または胎生→卵生への変化が起こったことが想像できるだろう。」
……卵生・胎生は生物の区分(進化)として、とても重要なのかと思っていましたが……混在することがあるんですね……。
この本を読んで感じたことは、サメはとても不思議な生物なんだなーということでした。「おわりに」には次のように書いてありました。
「サメの進化の歴史は約4億年におよぶ。これは、恐竜が出現し、絶滅した歴史よりもはるかに長いものだ。何を隠そう、サメは脊椎動物の歴史で最も古い時代に私たちの祖先と分かれ、独自の進化の道を選んだグループだ。その長い歴史の中で、サメは時間をかけて環境の変化に適応しながら、多様な生態や形態を獲得してきた。たとえば、ジンベエザメのようにプランクトンを食べるもの、イタチザメのようにスカベンジャー的な雑食性のもの、ミツクリザメのように顎を突出させて餌生物を捕食するもの、ニシオンデンザメのように超スローライフで数百年にわたる寿命を持つものなど、ここでは紹介しきれないほどだ。」
*
『知られざるサメの世界 海の覇者、その生態と進化』……サメの生態や分類、進化の道筋などについて総合的に解説してくれる本でした。冒頭には4ページのカラー写真(蛍光するサメとかシュモクザメの胎盤とかの貴重な写真など)もあります。みなさんも、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『知られざるサメの世界』