ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
天文・宇宙・時空
宇宙開発の歴史(川口淳一郎)
『宇宙開発の歴史 ~スプートニクからアポロ、ISS、はやぶさ、嫦娥まで』2025/7/1
川口淳一郎 (著)
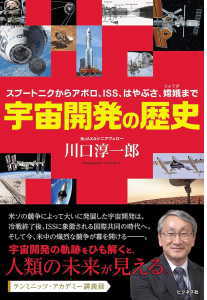
(感想)
米ソの競争によって発展した宇宙開発は、冷戦終了後、ISSに象徴される国際共同の時代へ、そして今や、米中の熾烈な競争へ……宇宙開発の歴史を振り返りながら、「なぜ宇宙開発が必要なのか」「これからどんな役割を果たすべきなのか」といった問いについて、日本の立場から考えている本で、主な内容は次の通りです。
はじめに
第1章 宇宙開発の流れを概観する
第2章 宇宙開発の初期段階 ~ロケット開発から人工衛星の打ち上げまで
第3章 人類が宇宙へ飛び出す時代へ
第4章 衛星探査機や惑星探査機の開発
第5章 冷戦の終了と変化する宇宙開発の目的
第6章 技術の確立、そして民間企業が参入へ
第7章 米ソとは異なる発展を遂げた日本の宇宙開発
第8章 太陽系の歴史を紐解く惑星探査
第9章 宇宙開発を継続するための「国際月探査」
第10章 宇宙開発における中国の台頭
第11章 政治の影響を免れない宇宙開発
第12章 月から火星へ ―Moon to Mars
第13章 地球にない宇宙資源を活用する時代へ
第14章 宇宙推進技術はどこまで進化したか
第15章 発展する宇宙空間利用と、進化する技術
第16章 宇宙開発は私たちの未来をどう変えるか
*
1969年、アメリカのアポロ11号が月面着陸に成功したことは有名ですが、世界で初めて月面に着陸した宇宙機は、旧ソ連のルナ9号(1966年打ち上げ)だそうです。
また驚かされたのが、宇宙開発での中国の怒涛の台頭っぷり! 「第10章 宇宙開発における中国の台頭」によると、中国は「長征5号」のような大型のロケットを自前で製造しているだけでなく、中国人宇宙飛行士が滞在している宇宙ステーションも建設・運用中なのだとか。さらに2020年7月には、火星探査機「天問1号」打ち上げ(21年5月に火星着陸。ローバーで探査)を行いました。さらに月についても……
「(前略)2024年に打ち上げられた「嫦娥6号」は月の裏側に着陸し、岩石や土壌のサンプル採集に成功しました。月の裏側に到達したのは、中国が初めてです。
月は、地球に対して常に同じ面を向いています。そのため、地球から直接、月の裏側へ電波を届けることはできません。そこで中国は事前に中継衛星「ジャッキョウ」を打ち上げ、地球からの電波を中継することで、月の裏側にいる探査機「嫦娥6号」と通信できるようにしたのです。地球・月のラグランジュ点L2点まわりのハロー軌道を利用していて、実に高度な軌道制御技術が運用されました。
さらに、月面でのサンプルリターンにおいても画期的な工夫をしています。月面上でサンプルを収めた上昇機が、月周回軌道上まで上昇して、帰還機とドッキングするという難易度の高いミッションをこなしたのです。」
……うわー、中国、凄いですね。だからアメリカに物凄く敵視されているわけだ。
アメリカは、現在、日本などとともに再び月を目指す「アルテミス計画」を行っていますが、その根底には、明確に「対中国」の意識があるようです。なお、この「アルテミス計画」では、参加国の間で守るべきルールとして、次の「アルテミス合意」が掲げられています。
「「アルテミス合意」には、探査や月面資源の利用はあくまで平和目的に限定すること、活動計画やデータは可能な限り公開すること、宇宙飛行士や装置の安全を相互に支援すること、他国の活動や遺産(アポロの遺構など)への妨害の禁止、宇宙ゴミの管理などが盛り込まれています。」
……ただし残念ながら月探査には明確なメリットがないようで……
「実は、月は人間が生活するには非常に厳しい環境です。真空であることに加え、半月間続く夜間には極寒となり、また大気や磁気がないために、太陽粒子線や宇宙線といった非常に強い放射線にさらされるリスクもあります。さらに、月面の砂は針状結晶質で人体にも有害です。つまり、月面に人が長期滞在することは大きな困難を伴うのです。」
……うーん、そうなんですか。しかもこの計画、いまや先行きが見通せない状況にあるようです。
「(前略)2025年1月に大統領に返り咲いたトランプ氏は、月面探査や火星探査を優先させるという理由で、この「アルテミス計画」の「ルナ・ゲートウェイ」建設の中止を提案しており、計画通りに進むのか、先行きが見通せない状況になっています。」
……とても残念ですね。ただ……「国際宇宙ステーション(ISS)」が老朽化のため2030年頃には運用終了見込みなので、それに代わる国際的な宇宙ステーションが欲しいような気がします……。
さて「第11章 政治の影響を免れない宇宙開発」には、宇宙開発と「軍事転用」の関係について、次のように書いてありました。
「宇宙開発とは何か。この問いに明確な答えを出すのは簡単ではありませんが、防衛と表裏一体の関係にあることは確かです。宇宙関連技術の蓄積は、ある意味で軍事転用とも隣接しており、たとえば小型の人工衛星を打ち上げることができる国であれば、大陸間弾道ミサイル(ICBM)を製造する技術力も持っているとみなされます。」
また「第15章 発展する宇宙空間利用と、進化する技術」には、重要性が高まっている「デプリ除去」(宇宙ゴミ処理)について、次のように書いてありました。
「たとえば、日本の企業アストロスケールは、ロケットの残骸に接近し、その様子を撮影することに成功しています。これは「近傍制御技術(Proximity Capability)」というジャンルの「ランデブー」で、指定の相対位置に接近して観察するサービスを指します。
これをさらに進めて、網などで対象を拘束し、自らともに大気圏へ再突入して処分する「能動的デブリ除去(Active Debris Removal:ADR)」も検討されています。
しかし、ADRは処分するデブリよりも大型の宇宙機が必要になり、コストが非常に高くつくのが課題です。」
……確かに、宇宙ゴミの処理は「高コスト過ぎ」なような気がしてしまいましたが、なんとこのADR技術は、対象衛星への電磁波などによる機能妨害や、一部機能の破壊などにも通じることから、防衛面での応用も考えられるそうです……これは……やっぱり進める価値がありそう……。
そして最終章の「第16章 宇宙開発は私たちの未来をどう変えるか」には、ワクワクするような未来予想が……
「(前略)多目的な宇宙船が、多様な目的地に向けて往復する時代がやってくると思っています。
その拠点となるのが「深宇宙港」です。これは、地球と太陽の引力が釣り合うラグランジュ点(L1点やL2点)に建設される宇宙港で、そこからさまざまな宇宙船が出港し、目的地に向かって、また戻ってくるための港です。地球から直接遠方の惑星に行くには莫大なエネルギーが必要ですが、深宇宙港で一度、宇宙船を乗り換えることで、高効率の推進機関を用いて効率的に探査を進めることができるようになります。」
……SFのような未来が、着実に近づいてきているんですね!
『宇宙開発の歴史 ~スプートニクからアポロ、ISS、はやぶさ、嫦娥まで』……宇宙開発の軌跡をひも解くと人類の未来が見える……宇宙開発が、資源を持たない日本にとって極めて重要な国家戦略となることを教えてくれる本で、とても面白く、また勉強にもなりました。宇宙に興味がある方は、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『宇宙開発の歴史』