ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
IT
図解まるわかり VR・AR・MRのしくみ(monoAI technology株式会社)
『図解まるわかり VR・AR・MRのしくみ』2024/10/17
monoAI technology株式会社 (著)
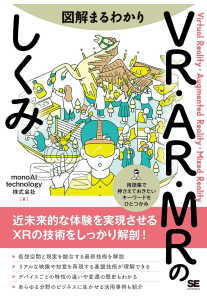
(感想)
仮想と現実を行き来しながら、さまざまな体験をできるようにするXR技術(VR、AR、MR技術)。XR技術の基本概念から、各技術の仕組み、開発手法や、実際の応用例まで、図解とともに詳しく解説してくれる本で、主な内容は次の通りです。
第1章 XRとは?~仮想現実と現実世界の融合~
第2章 VRの基礎技術~XRを実現する必須の要素~
第3章 XRを快適に体験する技術 ~質の高い没入体験を実現~
第4章 XR体験を豊かにする表現・コミュニケーション~ヘッドセットの外側へと広がる仮想世界~
第5章 XRの描画能力を向上させる技術~リアルな映像をより効率的に作り出すソフトウェアの進化~
第6章 XR技術をより深く理解する~根底にある3Dグラフィックス~
第7章 XRコンテンツ開発の応用~環境とツール~
第8章 XRアプリケーション開発の基盤技術~汎用性の高いプラットフォーム~
第9章 XRデバイスの技術と特徴~より使いやすいデバイスへの進化~
第10章 進化を続けるXR~業界別の実用例と今後の可能性~
*
見開きで1つのテーマを解説しているので、最初から順に読んで体系的な知識を得ることもできますし、気になるテーマやキーワードだけを読むこともできます。
「第1章 XRとは?」には、XRなどの各技術の簡単な解説がありました。それによると……
「XRとは、現実に存在しないモノを3次元のデジタル映像で再現し、デバイスを通じて、目の前に存在しているかのように見せるバーチャル技術の総称です。」
「ARとは、「Augmented Reality」の略称で、スマートフォンなどで撮影した映像に、デジタル情報を重ねて表示する技術を指します。
VRとは、「Virtual Reality」の略称で、VRゴーグルなどを用いて、仮想空間の中に自分自身が入ったような感覚を与える技術です。
MRとは、「Mixed Reality」の略称で、現実世界に付加した仮想のデジタル情報を操作することが出来る技術です。」
*
そしてXRと密接するテクノロジーの一部を紹介すると、次のような感じ。
・CGのリアルタイムレンダリングがXRの臨場感を生み出している
・センサーのトラッキング技術がXRの没入体験の質を向上させている
・ディスプレイの解像度とリフレッシュレートがXRの没入感を左右する
・5Gネットワークの高速大容量、多数同時接続、超低遅延の特性がXR体験の向上に大きく寄与する
・VR酔いやビジネスでのXR活用の課題解決には低遅延のリアルタイム通信が不可欠
・生成AIによるコンテンツ制作の効率化などAIがXRの発展を加速させる。
*
XRを実現するには大量・高速の情報処理が不可欠なので、それを効率的に実現できるような数多くの工夫がなされていますが、例えば視覚情報では、人間の視野の特性を生かして中心視野に高い解像度を確保して、効率的に高品質な映像を実現しているそうです(周辺の解像度は落としている)。
「第3章 XRを快適に体験する技術」では、触覚や音声、視線追跡などの他、VR酔いに関する技術について解説されていました。VR酔いを予防するための3つの手法には……
1)ルームスケール移動:現実空間と仮想空間での動きをリンクさせることで、VR酔いを防ぐ
2)トンネリング:VRヘッドセットの視野角を狭めることで、目に入る視覚情報を制限し、VR酔いを防ぐ
3)テレポーテーション:ユーザーが実際に移動せずに、瞬間的に仮想空間内を移動することで、VR酔いを防ぐ
……などが使われているそうです。
また「第4章 XR体験を豊かにする表現・コミュニケーション」では、ボイスチャットやビデオチャットの他に、観光地などでよく見かけるプロジェクションマッピングについても次のように説明されていました。
「プロジェクションマッピングは、特定のオブジェクトや空間の形状に合わせて映像や情報を投影する技術です。(中略)物体の立体形状や凸凹を考慮して映像をひずませることで、その物体に映し出されている変化が実際に起きているかのような臨場感を実現できます。」
……なるほど。そういうことだったんですね。
さらに「第5章 XRの描画能力を向上させる技術」では、アバターを人間のように動かす技術の他に、脳波を利用したインターフェース(脳波を読み取るEEGやPET、NIRSといった技術)についても解説がありました。電気信号、ブドウ糖の動き、大脳皮質の血流変化などさまざまな要素から脳波が測定できて、従来の機器を必要としない直観的な操作の実現が期待されているそうです……なんかちょっと怖いような気もしますが、体に障害があってもXRを快適に利用できるようになるのかもしれません。
そして最後の「第10章 進化を続けるXR」では、次のような業界別の実用例と今後の可能性が紹介されていました。
・VRを活用した正確なイメージ共有(仮想空間3Dモデルで製品を確認)
・VRで作業者のトレーニングと研修の効率化(練習用の材料費や設備費も削減可能)
・医療業界では、VRを活用することで継続的なリハビリテーション
・医学教育では、仮想空間内で患者の症例を再現し、実際の状況に近い環境で学習できる
・建設業界では、街の再開発でVRやARが使用される
・不動産業界では、賃貸や完成前の建物の内見がVRで行われる
・テーマパークのジェットコースターを仮想空間内で再現すれば、自宅にいながらVRを通じて乗車体験 など
*
……これらの実用例はどれも魅力的なものばかりなので、今後XR技術はどんどん進化して、社会に広がっていくんだろうなーと感じました。
そのためには、次の2要素が必要だそうです。
1)ハードウェアとソフトウェアの進歩、高速通信技術とセンサー技術の発展
2)リテラシーの向上と法整備、XRクリエイターの育成
*
「(前略)XR技術を適切に活用し、その恩恵を最大限に引き出すためには、社会全体のXRリテラシーの向上と法整備およびガイドラインの確立が不可欠です。」
……本当にそうですね!
『図解まるわかり VR・AR・MRのしくみ』……あらゆる業界で活用できて、今後私たちの身の回りでどんどん使われていきそうなVR・AR・MR技術の仕組みを学べる本で、とても参考になりました。XR技術に興味のある方はもちろん、未来社会について考えたい方も、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『図解まるわかり VR・AR・MRのしくみ』